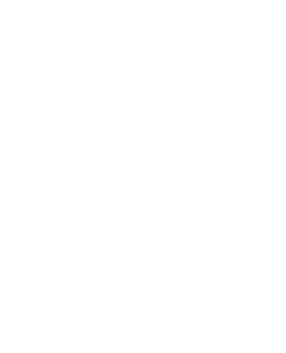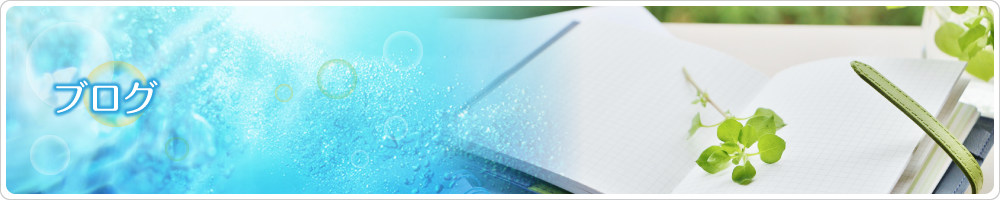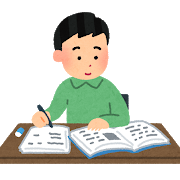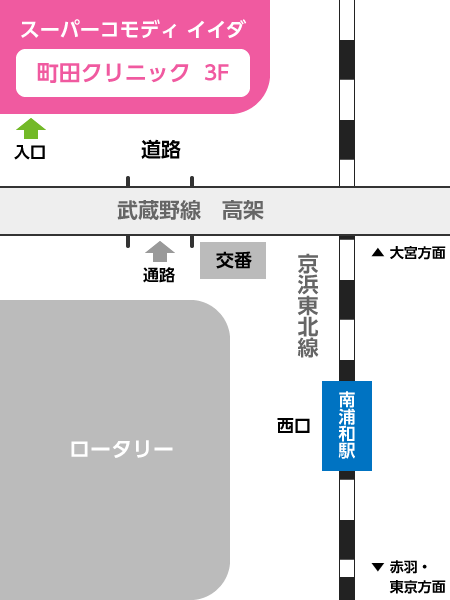今日は久しぶりに気持ちよく晴れた1日でしたね。
1ヶ月ぶりのドラマセラピーでは、動きながらうっすら汗ばむほどの陽気でした。
「ドラマ」というと、「しっかりと演技しなくちゃいけない」と思う方もいるかもしれませんが、ドラマセラピーは「別人になることを楽しむ」という感じです。
自分から離れてみることって、普段はなかなかできませんよね。
でも、ドラマセラピーの時間は、何にだってなれます。
ドラマの世界は自由ですから。
「別人」になって遊んでいると、不思議と動き方や喋り方、姿勢まで変わっていきます。
そうやって自由に「別人」を遊んでいるうちに、普段ならば口に出せないような言葉が口から出たり、感情を表現できたりするのです。
今日は、袋に手を入れて紙を引いてもらい、紙に書かれた「役(職業)」を互いに演じながら、相手が何役なのかを当てるというワークを行いました。
「魔法使い」と「小学校の先生」との会話(!!)など、普段はありえない会話が繰り広げられたり、、、
大笑いしたり、思わぬ共通点に驚いたり、、、
皆さん、すごく楽しまれていて、私も嬉しかったです。
「役と自分は全く違うと思っていたんですが、やっているうちに、私の中にも似た要素があったなと思いました。偶然に紙を引いたわけではなかったのかもしれないなとも感じました。」
「自分には息子しかいなかったのですが、今日は娘のいる気分を味わいました。子沢山のお母さん役ができて嬉しかったです。」
「魔法使いの役は楽しかったです。言葉じゃなくて、動きだけで魔法を使っている感じを体験できたのも楽しかったです。自由になれた気がしました。」
最後のシェアリングでは、そんなご感想も出ました。
来月は11・9の午後に行います。
別人になって、新たな体験をしてみませんか?
ドラマセラピーの時間に、ぜひいらしてくださいね。
お待ちしております。